

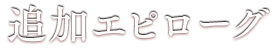
針葉樹の林を縫って延びる石段は、漂う霧に白く煙っている。 時折、山のどこかで立ち木に木刀を打ち込む鋭い音が響く。朝の剣の稽古――そのように思われたが、沙兆はこれを合図だと即座に察していた。 前よりも少し長く伸ばした栗色の髪を結い上げて纏め、濃縹(こきはなだ)の色無地に黒い袋帯を締めた和装で、彼女は山腹に細く通された道を歩む。 九州南部、四月初週。太陽の位置はまだ低く、山の空気は清冽なほどに肌寒い。それを気に留める風もなく、束ねられた菊の切り花を携えて、沙兆は段差のある切石の階段を滑るように登っていく。 あの日から――剣の街エスカリオより帰還を果たしてから、三ヶ月あまりが経っていた。*異界への門を通過し、沙兆(さてら)と十億主(ぎがす)が降り立ったのは、二〇〇〇年を目前にした聖夜に浮き立つ日暮れの渋谷の雑踏だった。 ふたりが駅前のスクランブル交差点に現れた時、周囲にはわずかながら驚きの波が広がっていた。最後の激闘からそのまま、身支度を調える間もなく帰ってきたのだ。軽装ながらも戦装束に身を包んだ沙兆は異様な形状の巨大な弓と、鈍い光沢を放つ生命の木の木剣を背負っている。十億主に至っては次元を超える際にドワーフから元の人間の姿に戻っており、人波から頭を飛び出させた巨漢が、丈の足りない板金鎧を着込んで交差点の中央に仁王立ちになっていたのだ。人目を引かないわけがなかった。 だが、向けられた奇異の目はすぐに街を彩るイルミネーションへと移り、ふたりへの人々の関心はほとんど失われた。長く行方の知れなかった漂流者の帰還と見るには、沙兆はあまりにも美しく堂々としていた。十億主の体躯は特別な神々しさを帯びていた。瑪守姉弟は文明社会に帰り着いた異世界の戦士たちではなく、クリスマスイブの夜に合わせて仮装をしているモデルかタレントであろうと判断されたのだった。 騒ぎにならなかったのを幸いに、ふたりは徒歩で帰路へと就いた。宵闇迫る青山通りを、彼らの足で三十分ほど歩けば赤坂御用地へと至る。誰に咎められることもなく、沙兆たちは目的地へと到達した。御用地に隣接する広大な敷地に構えられた屋敷――彼らの生家である瑪守本家の門を叩いたのは、西の空に残る橙色の光がようやく消え去る時分だった。 沙兆と十億主が帰参を果たしたとの報に、ほどなく瑪守家は蜂の巣を突いたような騒ぎに包まれた。連絡を受けた分家の者たちが続々と集まる中で、沙兆は泣きじゃくる末の妹・茉千(まきろ)をずっと抱擁してやっていた。柔らかで傷のひとつもなかった幼い掌は、新たな跡取りとして始めさせられていた稽古で、まめを潰して痛々しいありさまだった。 「つらい思いをさせたね、茉千。もう心配しなくていい。私がすべてお終いにするよ」 止め処(ど)なく溢れ出す涙を拭ってやりながら、沙兆は決意を新たにした。自分の胎内に宿った娘が、未来の出来事として言い残したことを――即ち、女系で連綿と繋いできた瑪守家の因習に終止符を打つことを。 一族の主立った者が集められた畳敷きの広間に端座し、沙兆と十億主は彼らに起こったことを簡潔に語った。現当主である母・姚(よう)は一段高くなった座で、娘と息子の荒唐無稽な報告に口を差し挟まず耳を傾けた。 四十代に入ったばかりの姚は、そうと見えぬほどに若々しく、武においても些かの衰えも見せていない。若き日には武道で沙兆に勝るとも劣らぬ成績を残し、今も欠かさず鍛錬を続ける現役の武芸者である。エスカリオに墜ちる以前、沙兆はこの母に勝つことができなかった。身体能力は打ち負かすに充分、センスでは上回る才を示しながらも、実戦経験の差と駆け引きの妙が、気づけば沙兆を絡め取って敗北へと追い込むのだった。母はまるで自分の力のすべてを知り尽くし、過不足無く使いこなして悠々と君臨する雌虎のようであった。 その姚には、子どもたちの所作を見ただけで理解できていた。彼らがこの現世のどこであろうと体得できぬ域にまで――極限の環境下で死線を潜らねば辿り着けぬ領域にまで、武人としての技量を引き上げて戻ってきたことを。ふたりの語る内容がどれだけ奇想天外であろうと、それが疑いなく真実なのだと姚は受け容れた。 沙兆は母に、是良人とのことは告げなかった。無論、今身籠もっているであろうことも。そして百萬郎(めがろう)が妹に、女性になってしまったことも。ふたりの話を聞き終えた姚が尋ねたのはひとつだけだった。 「その“えすかりお”から、もう帰る機会は得られないと解ったうえで、百萬郎は望んで残ったんだね? おまえたちも納得してるならそれでいい、あの子にとってはきっとね……大した冒険をしてきたじゃないか。おかえり沙兆、十億主。よく帰ってきた」 母の――千年近く続く瑪守家の当主を務める女傑の度量に改めて感服しながら、沙兆は考えていた。この母を打ち負かさなければならないと。武でも、人の器においても。*唐突に、視界が開けた。 立ち籠める靄で見通せなかった石段の山道が、大きく湾曲した先で登りを終えた。そこで樅(もみ)や赤松の木立は途切れ、開墾された緩やかな下り斜面となる。山肌を吹き抜ける微風が霧を掠い、午前の陽光を浴びた山々が沙兆の目に飛び込んでくる。 霧島連峰を一望するその山の中腹は、墓地であった。ある程度の間隔を置いて、古びた墓石が数十基並んでいる。不便な山中にありながら、いずれも手入れが行き届いているように見受けられた。 そこに足を踏み入れた瞬間、沙兆の耳にまた、立ち木を強く打つ音が届く。 ――観察されているな。 それは彼女の動向を報せるための合図だった。だが、沙兆は先刻承知している。この山に立ち入った瞬間から結界に――複数の目に監視されている区域(ゾーン)に足を踏み入れた感覚があった。あからさまな敵意ではないが、歓迎しているとも言えぬ硬質な気配の群れに包囲されたと、身体の奥底で警報が鳴った。 どのみち、覚悟の上だった。ここは余所者が気軽に訪れてよい地ではない。九州最南のここK県で、瑪守家と同じように長く武を受け継ぐ一族の墓所なのだ。 山のあちこちから続けざまに起こる撃剣の響きは、警告と威嚇のようだった。怪鳥の叫びに似た裂帛の気合いも聞こえてくる。しかし微塵も臆した様子を見せず、沙兆は墓の間の小径を進む。墓地の最奥は再び斜面に沿って登る石段が積まれており、その終端の高台には一際大きな墓碑が建立されていた。 磨き込まれてはいたが、ひどく古い時代の墓石だった。代々の当主の家系が葬られた墓はそこに間違いないと――自分が参るべき墓はそこだと沙兆は確信する。 墓に寄り添うように、一本の桜の古木がそそり立っていた。見渡す限り唯一の桜は、この地方ではもう花は終わっている時期であるにも係わらず、薄桃色の花片をつけたまま満開を保っている。何かの訪れをじっと待つかのように。 沙兆は墓碑の正面に立った。そこに刻まれている家名は龍仙。墓石の向こうに、遠く高千穂の峰が青く美しく聳えている。 一礼し、彼女は膝をたたんで腰を落とした。持参した仏花の束を供え、線香に火を点す。風はすでになく、煙は細く真っ直ぐに、澄んだ蒼天へと昇っていく。 目を閉じて、沙兆は一心に拝んだ。飛竜と混じって人の心を失い、是良人に討たれた龍仙達馬のために。 いつしか、あの木刀を打ち込む音は止んでいた。大気の中に張り巡らされた蜘蛛の糸のような幾つもの気配も、弛んで融け去ったかの如くに消えている。ただひとつを除いて――。 露わにしたうなじが、感覚器であるかに肌にちりちりと電気を走らせる。 ――近い。 沙兆が静かに顔を上げると、桜の幹の傍らに男が佇(たたず)んでいた。見事な気息の消し方だと彼女は感嘆する。男は最初からそこにいたのだ。あまりにも風景に自然に溶け込んでいて、殺気の類いの察知に敏感な沙兆は逆に見落としてしまっていた。 大柄だが痩身の、初老と思(おぼ)しき男であった。否、痩せているという表現は正確ではない。若い時分からの絶え間ない鍛錬でのみ獲得できる、薄く無駄のない強靱な筋肉が全身をくまなく覆っている。膂力よりも、速度と反応を高めることに特化した肉体の完成形がそこにあった。余剰をすべて削ぎ落とした印象が、男を本来の年齢よりも老け込ませて見せているのかも知れなかった。 男の容姿を語る上で何よりも大きな特徴は、額から頬にかけて、左目の上を通って深く残る太く古い傷痕だった。その傷を受けた際のものなのか、左の瞳は白濁して光を失っている。鋭い刃物に斬り裂かれたのではなく、厚みのある何かで抉られた痕であると思われた。 ここでようやく、沙兆は男が紋付き羽織と袴を身に着けていると気づく。それは葬儀の正装であり、彼女が山に入ってから報せを受けても用意が間に合わぬであろう出で立ちであった。果たしてどこから監視されていたのだろうか? 昨夜K空港に到着し、宿を取った時点で、あるいは――。 「瑪守家御当主・沙兆殿とお見受けしもす」 静かだが、鍔迫り合いに似た圧力を帯びた声だった。 「ご挨拶もせぬままここに参りました。ご無礼があればお許しください」 立ち上がった沙兆は深く頭を下げ、続けた。「――龍仙家の方ですね?」 「いかにも。達馬ン父になりもす」 彼女が予想した通り、男は龍仙達馬の父親――龍仙家の現宗主だった。そして達馬の名を出したということは、沙兆の墓参の意味にも気がついている。 「――倅(せがれ)はやはり、こことは別ン世界で死んでしもうたのですな」 「……はい。亡くなられた場に、立ち合っておりました」 この瞬間に、息子が生存しているやも知れぬという一縷の望みは完全に潰えた。龍仙の宗主は右目を閉じ、開いたままの見えぬ左目だけで天を仰ぐ。 「エスカリオ墜ち、半信半疑でおりもした。末の倅がひょっこり帰(もど)っくることもあるかと……じゃっどん、こいでやっとかっと冥土ば送ってやる踏ん切りがつきもした――」 黙ったまま沙兆は小さく頷く。そう、彼女は龍仙達馬の死を告知する使者として、その責務を果たしにやって来たのだから――。*大量失踪事件と異世界エスカリオの件は、沙兆たちの帰還からしばらくの間、世の耳目を集めることとなった。 あの日、瑪守姉弟の他にも、同じ世界・同じ時代に帰ってきた異邦人が何人かいたようだった。そちらは沙兆たちよりも大々的に捜索された行方不明者であったため、その彼らが突然戻ってきたことが騒ぎとなった。タブロイド紙に“現代の神隠しか?”とセンセーショナルな見出しが踊り、報道陣が生還者のもとに連日詰めかけた。そこで聞き出されたことの中でも、とりわけ大衆の興味を惹きそうな話題が記事として書き立てられ、テレビのワイドショーを賑わせた。ついには手記を出版する当事者も現れ、少なくない犠牲者を出した剣の街エスカリオへの異邦墜ちは広く世間に知られることとなった。 手記や証言に帰還のキーマンとして名前の挙がった瑪守姉弟にも取材を申し込む動きがあったが、それはすぐに止んだ。そればかりかエスカリオ墜ちに関連する報道全般が急激に下火になり、明けた年の寒さが緩む頃には、新しい情報が追加されなくなったこの件を殊更話題にしようとする者は、少なくともテレビや週刊誌では見られなくなった。 姚が手を回したのは明らかだった。要人の守り役として中世から続く瑪守家は、政界財界に強い影響力を持つ。それに頼ることは滅多にないが、多少の借りを作ることになっても母は、娘たちに深く関係するこの事件をそれ以上騒ぎ立てさせぬと決めたのだ。 それについては政府の意向も同じであるようだった。法治国家の運営を安定させるに当たり、突如異界への穴が開いてエスカリオ墜ちに巻き込まれるかも知れない、という不安を人々が必要以上に抱くことはマイナスでしかない。報道には、決して反感を買うほどにあからさまではないものの、じわりと締め付けるような圧力がかけられた。その見返りなのか、沙兆と十億主は何度か、瑪守家を訪問してきた政府筋の人間の聴取を受けさせられた。こうした超常事件に対応できる部署の新設が決まり、可能な限りの情報を得ておきたい、ということであった。 ただ、一時期の過熱した報道は、沙兆たちにとって迷惑なだけではなかった。 生還者への取材攻勢がまだ鎮静化していなかったその日、たまたま点いていたテレビの画面にそれは映った。 “だから、もう話すことは何もないっての” 記者たちに追われながら、ひとりの少女が不機嫌そうに叫んでいた。“やっと、心配かけっぱなしだった親に孝行できるんだからさー。これからママと買い物に行くんで、放っといてくんない? そいじゃねー!” 映像にはモザイクがかけられていたが、その声と黄色いニット帽は間違えようもない。沙兆は知らず自分が顔をほころばせていたことに気づいた。 ――そうか、アンナも同じ世界にいるのだな。そのうち、ギガスと一緒に顔を見に行ってやろう。*龍仙家宗主の左目は、八年ほど前の剣術仕合――否、果たし合いと呼ぶべき立ち合いで失われたものだった。 相手は、華親流剣術の裏伝継承者と言われ、現代において屈指の実戦剣法の使い手と名高い華親冬理――是良人の父その人であった。冬理は無謀と言うべき武者修行のために九州地方を巡っており、木刀での、命を賭けての仕合を受ける猛者を求めてこの地へと流れてきた。 龍仙もまた、平和な時代にあって真の武を求める者であった。薩摩藩御留(おとめ)流たる示現流剣術の流れを汲み、先祖伝来の技を休むことなく磨いてきた剣士にとって、冬理の申し出はそのまま己の望みでもあった。強敵と存分に剣を交えたい。双方命を落とすことも納得のうえで、思うさま自身の技を振るってみたい。その秘めたる願い、諦めざるを得なかった願望が叶うとあって、龍仙は華親冬理との仕合を承諾した。 ふたりの勝負は、火山活動を活発化させた新燃岳が噴煙を吐き、雪と灰が降る中で行われた。場所は中世の昔に噴火で焼失した霧島神宮・古宮址(ふるみやあと)。龍仙家一族によって人払いがなされ、中立の見届け人の立ち合いのもと、剣鬼たちは互いの矜恃にかけてぶつかり合った。 永劫を思わせるほどに対峙は長く、そして決着は刹那であった。蜻蛉の構えからの、二の太刀要らずの剣撃が冬理の頭蓋を砕いたと見えた瞬間、大きく振りかぶった異様な据え物斬りの構えの剣士の姿はぶれたように消えた。同時に冬理の木刀の切っ先が、龍仙の左目を縦に擦過し、額と頬の肉を削り落とした。骨にまでは達さなかったが、斬撃の衝撃は脳を揺らし、龍仙はそのまま昏倒した。生涯ただ一度の、完全なる敗北であった。 「そん果たし合いば、古宮址に忍んどった達馬は見てしもうた。ずっと、忘れられんごっなりよりもした。いつか俺(おい)も、華親冬理と立ち合(お)うてみたいと言うて――」 そう語る龍仙宗主の左目は、遠い追憶を見ているようであった。閉じられていた右目が開き、沙兆へと向けられた。 「あれは……倅は、悔いば残して死にゃせんかったですか」 その目を逸らさず受け止めて、沙兆は首を振った。 「ご子息は望む通りに、華親流と――華親冬理の技を継いだ者と真剣を交えました。そして、笑って事切れました。何ひとつ、未練を残さずに」 「……そう、でしたか」 見えぬ左目から、一筋の涙が伝い落ちた。 龍仙達馬は、父と華親冬理の死闘を目撃した時から、ただ生きるだけでは不幸せとなる運命を――ある種の呪いを抱え込んでいた。いつか己も身を焦がすような闘いの中で魂を燃やさなければ、死んでいるも同然と感じてしまう虚無の呪いを。 だから、短すぎる生であったとは言え、血を吐く努力の果てに養った技を望むままにぶつけ、死んでいった達馬は満足であろうと父は信じた。こと現代にあって、剣の家である龍仙の末裔の誰よりも幸福な最期であったと――。 穏やかな沈黙が流れた。その静寂が、聞こえるはずのない羽音を沙兆に感知させた。振り返ると、鼻先を掠めるように影が躍る。 それは青みがかった大きな黒揚羽だった。羽の尾状突起がふたつに分かれた珍しい姿のその蝶は、しばらく墓碑の周囲をひらひらと舞うと、桜の幹に沿って樹上へと昇っていく。 山の麓から、ごうと風鳴りが聞こえた。次の瞬間、山肌を駆け上がってきた春風が沙兆の後(おく)れ毛を乱し、桜の周囲で旋風(つむじ)を巻きながら黒揚羽のあとを追った。 爆発したが如く、すべての桜の花が瞬時に吹き散らされる。無数の花片は薄桃色の螺旋となって、青い空へと昇っていった。まるで竜が宿ったかのように。 その風に乗っていったのか、あるいは幻だったのか――黒揚羽はもうどこにも見当たらなかった。*九州に飛ぶ数日前、沙兆は瑪守家当主となった。 彼女が二十歳の誕生日を迎えた日、瑪守のしきたりに従い、彼女は当主の座を賭けて姚に挑んだ。組み手に勝てれば当主は次代へと受け継がれる決まりだが、多くの場合、成人したばかりでは実力で当代に勝てる見込みはない。現当主である母親に移譲の意志があれば、ここで故意に負けてやり、娘が新当主になるという儀礼的な意味合いもある。ただ、当代に引退する気がなければ、娘はそのままの立場で何人も子を産む例もあった。 そして姚は、沙兆に家督を譲り渡すつもりは毛頭なかった。 一週間前に挑戦の決意を告げられ、姚は万全のコンディションで試武に臨んだ。沙兆の才が申し分なく、自分をも超えるであろうことは認めている。しかし瑪守の家を繁栄させるには、まだ自身が当主として采配を振るったほうがいい――そう判断していた。その経験に基づいた観察眼で、手加減なしで戦えばまだ四、五年は負けないと値踏みもしていた。 ところが、蓋を開ければ沙兆は尋常な腕前ではなくなっていた。 異邦人としてエスカリオに滞在していた頃の、身体能力の底上げは失われている。ただし、あの増幅された状態で実戦を重ねた鍛練効果、及び開眼した技の精度は沙兆を、現世では到達できぬ域の達人――名人の呼称さえ足りぬレベルの武神へと押し上げていたのだ。それをある程度は見抜いていた姚の、予想を遙かに凌駕する領域にまで――。 しかも、沙兆はこの日のために真の力を隠し通してきた。同じく超人的な戦闘能力を獲得するに至った十億主にも言い含め、彼らが異世界で身に着けた力を決して見せぬよう努めた。すべては老獪な姚から実権を奪い取るために。 対策も完璧に練られていた。ただ一度の挑戦で確実に当主となるべく、沙兆は姚を研究し尽くしてきた。姚に油断はなかったが、打つ手があったとすればこの日の試武を、なんらかの理由をつけて受けぬことだけだったのであろう。 結果として、姚は娘に敗北を喫した。一族郎党が残らず集められた場で、言い訳もできず、難癖もつけられぬ形で完敗したのだった。 勝利を収めたうえで、沙兆は身籠もっていることを母に告げた。身重の娘に、完膚なきまでに負かされた――その衝撃に見舞われている間に、家督の継承を宣言し満座の承認を得た沙兆は、続けざまに瑪守家当主として初めての命を下した。 「私の代をもって、瑪守の女系継承は終わりとする。この場で私は瑪守家の解体を宣する」 一族の者たちは何が言い渡されたのか理解が追いつかずに暫(しば)し沈黙し、やがてそれは困惑と憤怒の叫びに変わった。当主の決定は絶対であることが瑪守の掟だった。これが覆されるとすれば新当主・沙兆が撤回するより他にない。彼らが沙兆の前に押し寄せて恫喝紛いの懇願をしようとした矢先、数多の怒号を圧する大音声(おんじょう)が轟き渡り、試武の場は再び静まり返った。 十億主の大喝であった。さながら獅子吼(ししく)のその怒声は、エスカリオの戦場では猛り狂う凶獣の動きさえも縫い止める。残らず胆の据わった剛毅の者であるはずの瑪守一族が、揃って縮み上がるほどの気迫がそこには篭められていた。 「四十年だ」 腹の底まで響く声で十億主は言った。「俺が一族の面倒を見る。これまでの業は続けていけるじゃろう。この先四十年は、俺は誰にも負けん。ただし、それまでに各々(おのおの)が新しい生き方を探せ。準備期間をくれてやる、ということよ――」 改めて目を向けると、十億主は高校を出たばかりの若僧などには到底見えなくなっていた。恵まれた肉体を、頑健なドワーフとなってとことんまで鍛え抜き、人に戻って生還した武道の怪物がそこにいた。十億主の言葉に偽りはなく、それが必ず守られるであろうことを誰もが信じさせられた。 もはや、異を唱える者はなかった。姚だけが怒りを露わにしたが、もはや彼女から、一族を従える力は失せていた。 その姚に、沙兆は深く頭を下げた。己を殺して瑪守家に人生を捧げ、自分たち姉弟を産んでくれた母に――。*「母は私を許してはくれないでしょう。守ってきたものを……瑪守の家を、私が壊してしまったのですから――」 後悔はないが、寂しさは残ると沙兆は思う。是良人を愛した自分を貫くために、そして茉千や生まれてくる百京(ゆき)のために、彼女は母を犠牲にしたのだ。百京はのちに姚と和解できる未来があると教えてくれたが、それは沙兆を許したうえでのことなのかは判らなかった。 「要らん心配(せわ)、でしょうな」 言って、龍仙宗主は初めて破顔した。剣以外のすべてを捨て去ったようなこの男に、こんな顔ができたのかと驚くほどに人懐こい笑顔だった。 「俺(おい)がこげん恰好(なり)でおはんを待っちょれたのは、昨日(きの)ンうちに姚殿に報せをもろうたからよ。娘が墓ば参らせてもらうで、よろしゅ頼みもすっちゅう。怒っとりゃあせん、憎んどりゃあせんよ」 「!――」 心がすっと軽くなり、つられて沙兆も思わず微笑んだ。固い蕾がひと息に開いたかのようだった。母の器は、やはりまだ超えられはしなかった。 「華親の孫(まごんこ)を産(う)んはいつになりもすかい?」 「九月の半ばには」 慈母の表情を湛(たた)えて、沙兆は蒼天を今一度見上げる。昇った太陽の日射しはもう、麗らかな南国の春そのものを思わせた。 ――そっちは変わらず寒いのだろうな。ゼラト、メガロ……私は何歩か進めたよ。これからも歩いていく。おまえたちも望んだ道をゆけ。どこまでも――。 溢れた涙に陽光が宿り、煌めく。濡れた瞳に映る空はどこまでも高く、澄み渡っていた。
